目次
- 世界と歩むためのパートナー、JICA
- 国際協力は遠い存在ではない
- 青年海外協力隊がもたらす学びと誇り
- 地域社会に根づく“国際交流の芽”
- SDGs時代に求められる役割
- 未来を育むホームタウンとして
1. 世界と歩むためのパートナー、JICA

JICA(国際協力機構)は、日本の政府開発援助を担い、途上国と手を取り合いながら課題解決を進める存在です。インフラ整備や教育、医療から環境保全まで、活動分野は広く、人々の暮らしに直結しています。その姿勢は単なる“援助”ではなく「共に学び、共に成長する」パートナーシップです。
2. 国際協力は遠い存在ではない

国際協力という言葉を聞くと、遠い国での出来事に感じる人も少なくありません。ですがJICAは、東京や横浜をはじめ全国各地に国際センターを設置。地域住民が研修員と交流したり、国際理解プログラムに参加したりする機会を提供しています。つまり、JICAは「世界を知る窓口」として、私たちの身近に存在しているのです。
3. 青年海外協力隊がもたらす学びと誇り

1965年に始まった青年海外協力隊は、JICAの象徴的な取り組み。20代から30代の若者が、教育・農業・保健医療などの現場で力を尽くしてきました。現地での経験は、彼ら自身の成長を促すだけでなく、帰国後には地域に還元されます。授業や講演を通して“生きた国際経験”が語られるとき、子どもたちに新しい夢が芽生え、地域に誇りと刺激が生まれます。
4. 地域社会に根づく“国際交流の芽”

全国のJICA拠点や帰国隊員の活動によって、日本の町々で国際交流の芽が育っています。地方の学校でアフリカの教育事情を学んだり、地域イベントで海外の料理を体験したりする。そうした小さな体験の積み重ねが、「自分のまちと世界はつながっている」という実感を育てます。
5. SDGs時代に求められる役割

世界が気候変動や格差、難民問題といった複雑な課題に直面するなか、JICAはSDGsの達成に向けて国際社会と連携しています。その活動は、単に海外支援にとどまらず、日本の地域にも新しい価値観や実践をもたらします。持続可能な未来を築くため、地域から世界へと響くアクションが広がっていくのです。
6. 未来を育むホームタウンとして

JICAの活動は、国際協力という大きなテーマを、地域の暮らしにまでつなげています。それは「遠い世界の出来事」を「私たちの物語」に変える営み。日本各地のホームタウンが世界と手を取り合うことで、未来を共に築く力が生まれるのです。

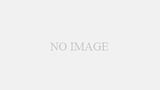
コメント